透析を受けている方の中には、「足がむくみやすい」「傷が治らない」「最近足先の色が変だ」といった悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
透析患者さんでは血流の悪化や糖尿病の影響などにより、足の潰瘍や壊疽が起こりやすく、最悪の場合、下肢切断に至ることもあります。
私は整形外科医として透析クリニックで日々診療に携わっていますが、“もっと早く気づいていれば”と思うケースに何度も出会いました。
この記事では、透析患者に多い足のトラブルと、それを防ぐための実践的な「フットケア」方法を、エビデンスを交えながらご紹介します。
1. なぜ透析患者さんに足の病変が多いのか?
透析を受けている患者さんでは、以下の理由から足の潰瘍や壊疽(えそ)などの足病変リスクが非常に高いとされています。
✅ 末梢動脈疾患(PAD)の合併
透析患者の約4割以上にPADの所見が見られるという報告もあり、足先への血流が不足し、治りにくい傷ができやすくなります(J Vasc Surg. 2012)。
✅ 糖尿病性神経障害
糖尿病を併発している透析患者では、痛みや熱さ・冷たさを感じにくくなり、小さな傷に気づきにくい状態になります。
✅ 免疫力・栄養の低下
透析治療中は体の抵抗力が下がりやすく、さらにアルブミンや亜鉛などの栄養低下があると、感染リスクや治癒遅延を招きます。
2. よくある足のトラブル
- 足潰瘍:足裏やかかとなどにできる慢性的な傷。感染の温床に。
- 壊疽(えそ):血流不良により足趾が黒く変色・壊死。
- タコ・ウオノメ:圧力が集中し、皮膚が硬くなって傷の原因に。
- 白癬(水虫)・皮膚感染:免疫低下で悪化しやすく、潰瘍に発展することも。
3. フットケア実践ガイド【エビデンスに基づくセルフケア5ステップ】
透析患者さんにこそ習慣にしてほしい、科学的根拠に基づいた日常的フットケアを紹介します。
◆ Step 1:毎日の足チェック
- 見る: 足の裏・足指の間・かかと・爪の状態をチェック。
- 鏡を使って裏側まで観察。
- 【IWGDF(International Working Group on the Diabetic Foot)では、毎日の自己観察が最重要の予防策とされています。】
◆ Step 2:ぬるま湯で優しく洗浄
- 温度は38℃前後。10分以内で短時間に。
- 石けんは低刺激のものを使用。
- 洗った後は清潔なタオルで水分を完全に拭き取る。
【出典】J Jpn Soc Dial Ther. 2018:透析患者における足指間湿潤は感染リスクと相関。
◆ Step 3:適度な保湿ケア
- 足の甲・かかとに尿素系やワセリン系保湿剤を使用。
- 足指の間は塗らない(蒸れやすくなるため)。
【参考】Diabetic Foot Journal 2016:皮膚バリア機能の維持が潰瘍発生率を有意に下げると報告。
◆ Step 4:正しい爪の手入れ
- 爪は深爪を避け、真っすぐに切る(スクエアカット)。
- 爪が硬くて切れない、視力が低下していて不安な場合は、医療者に相談。
◆ Step 5:靴・靴下のチェックと工夫
- 靴の中に異物がないか確認。
- 靴はつま先が広く、足全体を覆うタイプを選ぶ。
- 靴下は綿素材、締めつけが少ないもの。
4. 医療機関と連携した“攻めのフットケア”
以下のようなサポートを活用することで、足病変の重症化を防ぐことができます。
- 定期的なフットチェック(足病外来や整形外科)
- ABI(足関節上腕血圧比)や血流評価
- 壊死・潰瘍のデブリードマン(壊死組織除去)
- 感染対策(抗生剤・局所処置)
- 必要に応じた血管内治療や装具療法
5. 整形外科医から患者さんへ伝えたいこと
「こんなことで相談していいのかな?」
そう思って受診を先延ばしにしてしまう患者さんが非常に多いです。
けれど、小さな傷も、透析患者さんにとっては命取りになりかねません。
日々の観察とセルフケア、そして医療機関との連携こそが、足を守る最善策です。
おわりに:足は命を守る“窓口”です
透析患者さんにとって、足は単なる身体の一部ではなく、「生活の質」と「命」を左右する重要なパーツです。
どうか今日からでも、自分の足を毎日観察する習慣を始めてみてください。
「気になる傷」「見慣れない変色」があれば、ぜひ早めに医療者へご相談を。




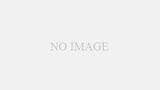
コメント