リディアードのランニング・バイブル──走ることの原点に立ち返る本
高校時代、部室の棚に一冊の本がありました。
タイトルは『リディアードのランニング・バイブル』。
当時はまだインターネットも普及しておらず、練習メニューは顧問の先生が組むのが基本でしたが、部活では「free」という日もあり、自分でメニューを考える必要がありました。そんなとき、練習の指針となったのが、部活の先輩が持ってきたこの本です。リディアードの理論を読みながら、「どうすれば強く、速く、長く走れるのか」を皆で試行錯誤していました。
リディアード理論の核心
アーサー・リディアードはニュージーランド出身の名コーチで、多くのオリンピックメダリストを育てた人物です。
彼のトレーニング理論は、**有酸素のベースをしっかり作り、その上にスピードや調整を積み重ねていく段階的トレーニング(Periodization)**にあります。
- 有酸素期(ベース作り):長距離をゆっくり走り、心肺と脚を鍛える
- 丘陵走(ヒルトレーニング):坂道を使って筋力と持久力を強化
- スピード期:インターバルなどでスピードを磨く
- 調整期:試合に向けて仕上げる
この流れは現在のトレーニング理論にも脈々と受け継がれています。
ダニエルズ理論との共通点
近年は「ダニエルズのランニング・フォーミュラ」が定番の一冊として知られていますが、その根底にある考え方――有酸素能力の重視、トレーニングの段階構成、走行ペースの明確化――は、すでにリディアードの時代に形づくられていました。
つまり、最新理論をたどると最終的にリディアードに行き着くのです。
科学的な表現こそ変わっても、ランニングの本質は半世紀以上前から変わっていません。
今あらためて読み返して
大人になった今、再びこの本を手に取ると、高校時代に感じた“走る楽しさ”と“自分で考えて走る自由さ”を思い出します。
ページをめくるたびに、当時の汗の匂いや、部活帰りの夕暮れを思い出すような感覚。
リディアードの理論は、単なる練習法ではなく、自分の脚で未来を切り開く哲学でもありました。
この本は、これからもずっと本棚に置いておこうと思います。
人生のどこかでまた走りたくなったとき、きっとこの本を開くでしょう。

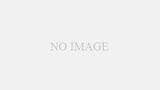
コメント